| きもの継松庵つぎたに Tel.079-245-2928 心のふれあいを大切に 継谷 芳久 とくとく情報をお伝えする事で安心して お召しいただくご参考になれば…。 |
生活様式の変遷と共に消えゆくものがあります。例えば「火鉢」や「かまど」等。でも残さなければならない「日本の心と形」。 珠算、書道、色々とあるでしょうが私はその代表が「きもの」であり「畳」ではないかと思います。日本が世界に誇れる民族衣裳「きもの」を通して、今後とも「良き伝統・文化」を次世代に伝え継げれば幸いです。 「きものが着た-い」。でもTPOがわからない、なにをどのように準備したらよいの。着た後の整理はどうするの。なぜ洋服のようにハンガーに吊るしてクローゼットに掛けて長期間保管しないの。「きもの」や「帯」「コート」のたたみ方がわからない。色々お知りになりたい事が有ると思います、そういう素朴で基礎的な疑問や質問にお答えができたらと考えています。 より専門的なことは、きもの研究家、民族衣裳専門の先生方が大勢いいらっしゃいますし、皆様すごく良い著書やホームページ等をお持ちですのでどうぞそちらをご参考にして下さい。 |
||
| 今日は。 |
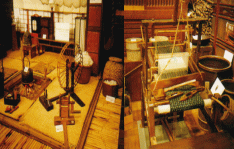 癒しぬくもりのあるくらし 和気町歴史民族資料館展示 |